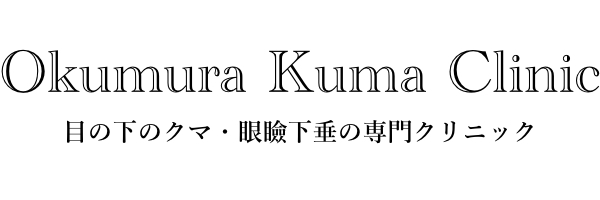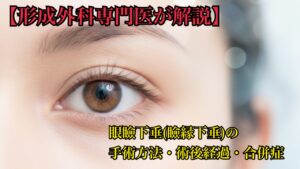こんにちは。
東京(有楽町・銀座)の東京日帰り手術クリニック/シンシア銀座院で、眼瞼下垂やまぶたのたるみ治療を専門に行っている形成外科・美容外科・眼形成外科の奥村 仁です。
まぶたの症状で悩む患者様は、
「眼瞼下垂かどうかわからない…」
「手術で本当に見た目も良くなるの?」
「どの手術が自分にとって一番いいのか知りたい」
といった、機能面と美容面、両方の不安を抱えていらっしゃいます。
当院は、眼の機能改善と自然で美しい仕上がりの両立にこだわります。今回は、あなたが抱える不安を解消し、納得のいく治療へ進むための診断から手術決定までの5つのステップを、専門医の視点からご紹介します。

ステップ1: 「困りごと」の深掘り ― 正確な診断への第一歩
まず、あなたの日常で起きている「困っていること」を具体的に整理しましょう。
- 目の機能の不調:
- 視野が狭く、上方が見づらい(運転や家事に支障がある)
- まぶたを持ち上げるクセがあり、額にシワが寄る
- 頭痛や肩こりがひどい(無理に目を開けようとしているサインかもしれません)
- 目の検査の時にまぶたを上に持ち上げられる
- 見た目の変化:
- 昔より二重幅が狭くなった、逆に広くなった
- 目尻の皮膚が覆いかぶさり、疲れて見える
これらの症状は、まぶたを開ける筋肉(挙筋・ミュラー筋)のゆるみや皮膚のたるみが原因かもしれません。あなたの症状を整理することで、その後の診察がよりスムーズになります。
①発症時期
⑴子供の頃から
⑵成人以降 年前から
②症状
⑴瞼が重たい・開きづらい
⑵上方が見えづらい,瞼を手で持ち上げると見えやすい
⑶上まぶたの奥が痛い
⑷頭痛,肩凝り
⑸症状に著明な日内変動がある
●既往歴等
①眼球,眼瞼関連事項
⑴コンタクト使用歴(ソフト・ハード 年)
⑵視力・乱視度
⑶緑内障
⑷白内障
⑸ドライアイ
⑹眼球・眼瞼の外傷,手術歴
②病歴
甲状腺機能亢進症,脳梗塞,高血圧,糖尿病,心筋梗塞,不整脈等
③使用薬剤
⑴緑内障(プロスタグランジン関連点眼薬)
⑵前立腺肥大症(アドレナリン拮抗薬)
⑶精神安定剤,抗不安剤(ベンゾジアゼピン系薬剤)
⑷抗血栓薬(抗凝固薬・抗血小板薬), 血管拡張薬
問診から分かること
①発症時期
⑴子供の頃から→先天性→まぶたを開ける筋肉(上眼瞼挙筋)の動きが悪い人が多く,吊り上げ術が必要となる症例もあります.
⑵成人以降 年前から→後天性→発症してから長期間放置していると治りにくくなります.
●既往歴
①眼球・眼瞼関連事項
⑴コンタクト使用歴(ソフト・ハード 年)
→ハードコンタクト使用歴が長い人に眼瞼下垂症が起こる事があります.コンタクトをはずす時にまぶたを横に引っ張る事が多いため,徐々に上眼瞼挙筋腱膜が伸びたり,瞼板から外れて眼瞼下垂症を引き起こします.左右差を認める事も多いです.手術後には,スポイト等の補助器具を使い,まぶたを横に引っ張らないでコンタクトを外せるようにして頂きます.
②症状
⑴瞼が重たい・開きづらい→眼瞼下垂による主症状です.
⑵上方が見えづらいが瞼を手で持ち上げると見えやすい→緑内障等で上方の視野欠損がある場合,まぶたを手で持ち上げても見えやすくなりません.
⑶ 上まぶたの奥が痛い→まぶたを開ける時,上まぶたの奥にある上眼瞼挙筋やミュラー筋が強く収縮し続けると痛みを生じます.
⑷頭痛・肩凝り→まぶたが開きづらくなると,無意識に歯を食いしばったり,眉毛を上げて見ようとします.その際働く側頭筋や後頭前頭筋が過度に収縮し続ける事により緊張性頭痛や肩凝りが引き起こされます.しかし,頭痛や肩凝りには,まぶた以外の原因もあるため,眼瞼下垂術後に完全によくなるわけではありません.
⑸日内変動(午前中はまぶたが開きやすいが,午後になるとまぶたが開きづらい)→日内変動が顕著だと重症筋無力症の可能性があります.
⑵視力・乱視度
→手術による眼瞼と眼球の接触圧が変わり乱視が変化する事があります.術後3〜6ヶ月で検眼して,眼鏡やコンタクトの調整をして頂きます.
⑶緑内障
→緑内障の第一選択薬のプロスタグランジン関連薬で眼瞼下垂や眼瞼陥凹を起こす事があります.
⑷白内障
→乱視等が術後変化しやすいため眼瞼下垂症の手術を先に行い,3〜6ヶ月して術後経過が安定してから検眼結果を元に白内障する事をお勧めしています.
⑸ドライアイ
→術後一時的にドライアイ症状が強くなり,半年程度で術前と同じ程度まで回復します. 眼が大きく開いて涙が蒸発しやすくなり, 涙を排出するポンプ機能が改善されるためだと考えられます.
⑹瞼の外傷や眼球の手術で使用される開瞼器等で上眼瞼挙筋や腱膜が損傷されると,眼瞼下垂症となります.
②治療中の全身疾患
●甲状腺機能亢進症
→片側性の眼球突出を認めると,反対側がヘリング現象により眼瞼下垂症になる事があります.
●脳梗塞等
→動眼神経麻痺を起こすと,動眼神経由来の上眼瞼挙筋の動きが悪くなり,眼瞼下垂となります.
●高血圧,糖尿病,不整脈,心筋梗塞等
→治療中の疾患がある場合には,主治医に局所麻酔手術の可否,周術期の注意点について確認を取ります.
③使用薬剤
●緑内障点眼薬プロスタグランジン関連薬(キサラタン®、タプロス®、トラバタンズ®、ルミガン®)→ PAP(プロスタグランジン関連眼窩周囲症)と言われ,副作用に眼瞼下垂や眼瞼陥凹を認めます. 上眼瞼挙筋の働きを弱くする副作用があります.
●前立腺肥大症(アドレナリン拮抗薬)
→ミュラー筋の収縮力を低下させ,眼瞼下垂の原因となりえます.
●精神安定剤,抗不安剤(ベンゾジアゼピン系薬剤)
→長期投与により,眼瞼下垂と同じように開瞼障害を起こす眼瞼痙攣を誘発する事があります.
●抗血栓薬
抗凝固薬(血流停滞部のフィブリン血栓抑制)
抗血小板薬(動脈硬化部の血小板凝集抑制)
●血管拡張薬
→抗血栓薬や血管拡張薬は術中,術後出血の原因となりうるため,主治医に確認をとった後,休薬して頂く事が多いです.
ステップ2: 形成外科専門医による多角的な診断
手術の成功は「原因の特定」にかかっています。当院では、機能回復だけでなく、将来の美しさまで見据えた精密な診断を行います。
チェックポイント
- **瞼縁下垂(まぶたの縁の位置)**の正確な評価
- **皮膚下垂(まぶたのたるみ)**の程度とバランス
- 根本原因の特定(挙筋腱膜、ミュラー筋、皮膚の余り、脂肪など)
これらの診断を通じて、機能改善(視野の回復、頭痛・肩こりの軽減)と美的改善(自然な二重幅、たるみの改善)の両面で、どのような結果が期待できるかを具体的に予測し、共有します。
ステップ3: 安全への配慮 ― 手術のための全身状態の確認
手術を希望される方には、安全性を最優先に、全身の健康状態を詳しく確認します。
既往歴、服薬状況、血圧、糖尿病、心臓疾患など、あらゆるリスクをチェックし、日帰り手術を安全に行えるかを慎重に判断します。
ステップ4: 原因に合わせた「最適な術式」の決定
眼瞼下垂・皮膚下垂の治療は、原因に合わせて術式を組み合わせることが重要です。当院では、形成外科・眼形成外科の専門知識に基づき、最適な治療計画をご提案します。
| 状態 | 主な手術法 | 期待できる効果 |
| 瞼縁下垂(開瞼力の低下) | 挙筋前転術、ミュラー筋短縮術など | 開瞼力の根本的回復。眠そうな目の印象を改善。 |
| 皮膚下垂(皮膚のたるみ) | 眉下皮膚切除術など | 余分な皮膚を切除し、自然な二重ライン・目元の若々しさを再構築。 |
【専門医のこだわり】 両方の問題がある場合も、あなたにとって最も効果的かつ負担の少ない治療フローをフローチャートに沿ってご説明します。
- 一般的に気になる症状(瞼縁 or 皮膚)を優先します。
- 片方の手術だけで満足いく改善が得られるケースもあります。
ステップ5: ダウンタイムまで考えた無理のない計画
日帰り手術で翌日以降の日常生活を考慮し、手術後のスケジュールも一緒に計画します。
| 経過日数 | 状態 | 日常生活の目安 |
| 手術当日〜3日 | 腫れ・内出血が強い時期 | ご自宅での安静・冷却に専念ください |
| 4日目〜6日目 | 腫れが落ち着き始める | リモートワーク・軽作業などは可能です |
| 7日目 | 抜糸・腫れが7割程度改善 | 眼鏡でカバーすれば出勤も可能な方が多いです |
| 14日目以降 | 腫れ8割改善・内出血消失 | 接客・営業などもほぼ問題なく行えます |
眉下切開手術の傷あとについて 3週間程度は傷がやや目立つ時期がありますが、その後はお化粧で十分カバーできるレベルまで落ち着きます。
機能と美しさ、両方を追求したいあなたへ
眼瞼下垂・まぶたのたるみ治療で最も大切なのは、「目の開き」という機能と、「自然で美しい」という審美性、この両方を追求できる医師と出会うことです。
当院は形成外科・美容外科・眼形成外科の専門性を活かし、あなたの症状を正確に診断し、ご希望と生活スタイルに合わせた最適なオーダーメイド治療プランをご提案します。
目の開きやまぶたのたるみでお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。 手術が必要かどうかの診断だけでも歓迎いたします。
金曜日 東京日帰り手術クリニック(有楽町)
土曜日 コスメディカルクリニックシンシア銀座院